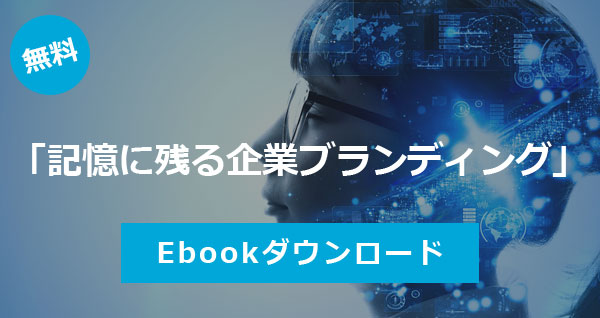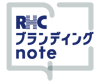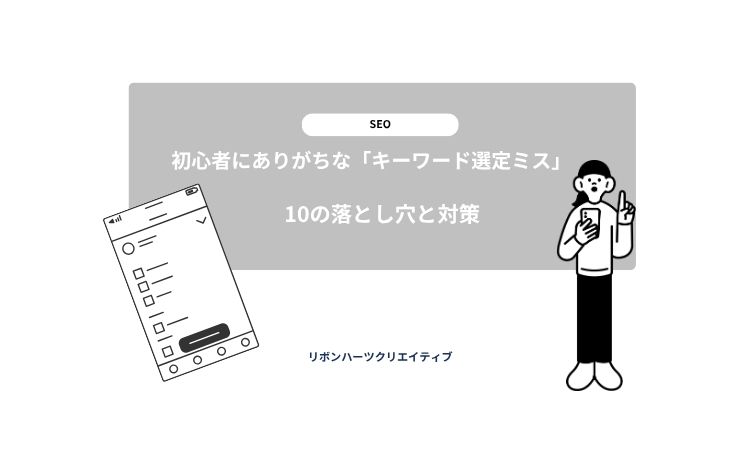「他の人はこちらも検索」とサジェストキーワードの違いと活用術|検索意図を深掘りしてSEOに強くなる方法
コンテンツマーケティング
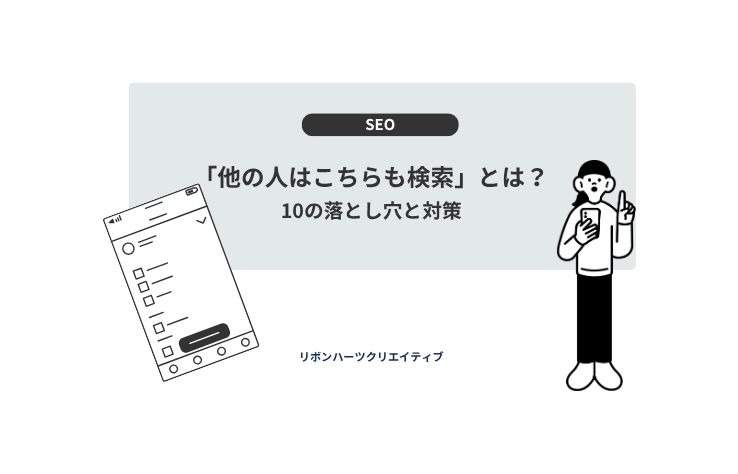
Google検索でよく目にする「他の人はこちらも検索」という表示。何気ない機能に見えますが、実はユーザーの興味関心や検索行動の裏側を読み解くための重要なヒントが詰まっています。本記事では、その仕組みやサジェストとの違い、SEOへの活用法までをわかりやすく解説します。
Googleの「他の人はこちらも検索」とは?
Googleの「他の人はこちらも検索」は、検索結果ページに表示される関連キーワードの提案機能です。
ユーザーが検索後にすぐ戻った場合などに表示され、検索意図をより深く探るためのヒントを与えてくれます。この機能を活用することで、ユーザーが求めている情報にたどり着きやすくなるだけでなく、Webサイト運営者にとっても、より効果的なSEO対策やコンテンツ改善の手がかりとして活用できる点が注目されています。
「他の人はこちらも検索」の表示場所と仕組み
この機能は、検索結果ページに戻った際、クリックしたサイトの下に出現します。戻る操作をトリガーとして、似た検索を行ったユーザーの履歴から関連語句を提案していると考えられます。
表示されるキーワードはGoogleが自動で選んでおり、ユーザーの行動に応じて変化します。つまり、検索結果ページを補完する役割を担う動的な表示機能です。
なぜこの機能が表示されるのか?Googleの意図を解説
Googleは常に、ユーザーの検索体験をより満足のいくものにすることを目指しています。「他の人はこちらも検索」という提案は、最初の検索結果に対するユーザーの行動――たとえば、短時間で離脱したり、再検索したりした行動――を元に、「別の情報を探している可能性がある」と判断したときに表示されます。
つまり、ユーザーが求める情報にたどり着けなかったときの“補助検索”の役割を果たしているのです。これにより、検索意図に合致した情報へ誘導しやすくなります。
クリックデータが影響する?仕組みと表示条件を解説
「他の人はこちらも検索」の表示は、過去のユーザーのクリックデータが重要な役割を担っています。
具体的には、同じページを訪れた他のユーザーが次に検索したキーワードや、その後にアクセスしたページなどの情報が収集され、関連性の高いクエリとして提案されるのです。
また、表示条件には「すぐに戻る」などのユーザーの行動データも関与しており、単純なアルゴリズムではなく、行動パターンに基づいた分析が背景にあります。つまり、これは静的な機能ではなく、検索者のニーズにあわせて変化するダイナミックな仕組みです。
サジェストキーワードとの違いとは?
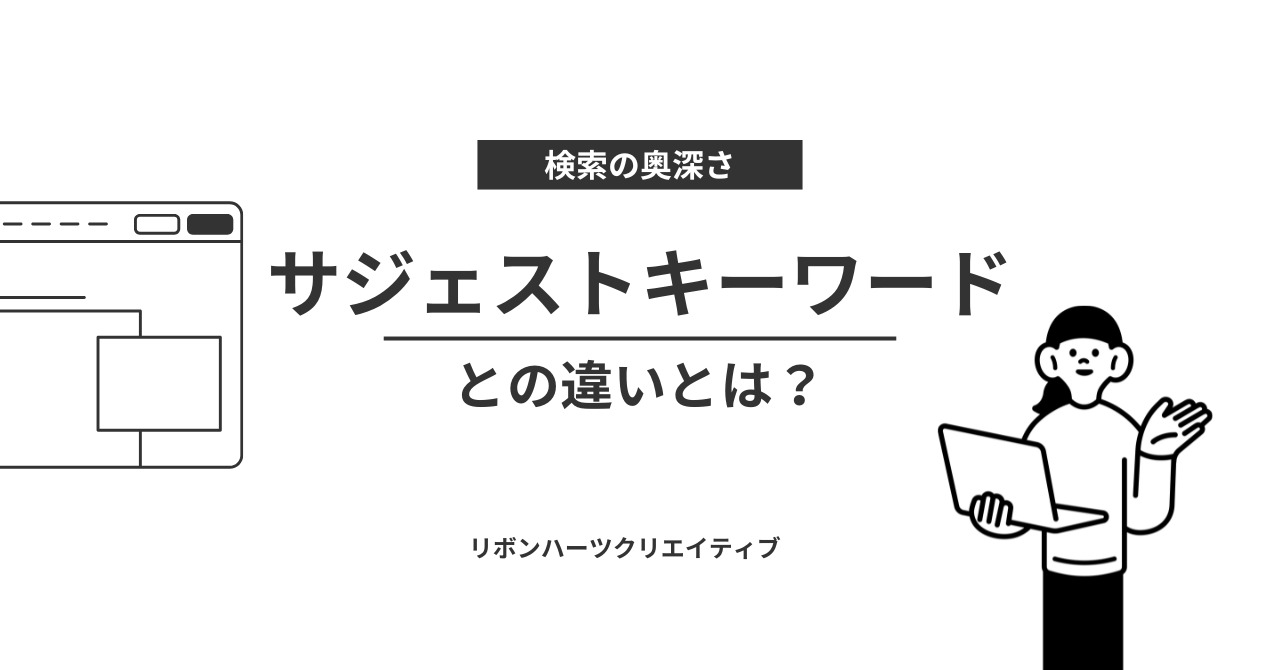
「他の人はこちらも検索」と混同されがちなのが、Googleサジェスト(自動補完キーワード)です。どちらも関連キーワードを提示する機能ですが、仕組みや使われ方はまったく異なります。それぞれの違いを理解すれば、より効果的にSEO対策に活かすことができます。
Googleサジェストと「他の人はこちらも検索」の関係性
サジェストは、ユーザーが検索窓に文字を入力した際に表示される補完キーワードのことです。一方、「他の人はこちらも検索」は、検索後に特定の行動(クリック→戻る)をしたときにだけ表示されます。
両者はどちらも検索ニーズに基づいた情報ですが、サジェストは予測、もう一方は補足という性質を持っています。目的も表示のタイミングも異なるため、それぞれ別の視点で活用する必要があります。
表示されるタイミング・データの出どころはどう違う?
Googleサジェストは、検索ボックスに入力したときにリアルタイムで表示されます。そのデータ元は、検索頻度やトレンドなど、大量の検索ログに基づいています。
一方、「他の人はこちらも検索」は、ユーザーが検索結果をクリックし、再び戻った際に初めて出現します。その根拠は、直前の行動や過去ユーザーの検索履歴など、行動ログに基づいた情報です。表示条件や目的が大きく異なるため、混同せずに使い分けましょう。
「他の人はこちらも検索」から分かる潜在ニーズ
この機能には、検索ユーザーの“言語化されていない悩み”が反映されています。たとえば、初回の検索で満足できなかったときに表示されるため、「本当に求めている情報」へのヒントとなるのです。
つまり、「他の人はこちらも検索」には、検索者の“次の行動”が予測されているため、コンテンツ設計のヒントや、ユーザーがどこで迷っているのかを読み解く手がかりになります。
サジェストから得られる具体的な検索行動のヒント
サジェストに表示されるキーワードは、今まさに検索されている言葉や、過去に多く検索された組み合わせです。たとえば「転職」と入力すると「転職 30代」「転職 面接」などが出てくるように、ユーザーの行動傾向を可視化してくれます。
これらはニーズが顕在化しているため、タイトルや見出しの作成にもすぐに活用できます。記事構成の初期段階では、非常に実用的なデータといえるでしょう。
コンテンツ制作にどう活かす?SEO戦略のヒント
「他の人はこちらも検索」やサジェストなどから得られるキーワード情報は、コンテンツ設計において非常に有効です。検索ユーザーが求めている情報や疑問の流れを把握することで、より実用性の高い記事づくりが可能になります。
関連クエリの抽出方法と使い方
コンテンツ制作の第一歩は、ユーザーがどんな検索クエリを使って情報を探しているかを把握することです。「Google Search Console」や「キーワードプランナー」などの無料ツールを使えば、実際に使われた検索語句を確認できます。
これらのクエリは、ユーザーのニーズを具体的に示しており、見出しや本文の内容に反映することで、検索意図に合った記事がつくれます。検索回数だけでなく、“どういう気持ちで検索されたか”という背景も意識して選びましょう。
「他の人はこちらも検索」から記事構成を逆算する方法
「他の人はこちらも検索」に出てくるワードは、検索ユーザーが“最初の検索で満足しなかったとき”に表示されるものです。これはつまり、1つのテーマに対してどんな疑問や関連話題があるかを示す手がかりになります。
たとえば、「副業 税金」というキーワードに対して「副業 確定申告 必要?」などが表示されていれば、記事内でその疑問にも触れるべきです。こうして表示ワードをもとに構成を逆算することで、網羅性とユーザー満足度を両立できます。
タイトルや見出しに応用する具体例
抽出した関連キーワードや表示ワードは、タイトルや見出しに活用することでクリック率を高める効果があります。たとえば、「転職 面接」であれば「転職面接でよくある質問10選」といった形で検索意図に直結する言葉を取り入れるのがポイントです。
また、検索結果画面で目を引くよう、数字や結論を入れるのも効果的です。「他の人はこちらも検索」に出る語句をヒントに、検索者の「次の一手」を見越した見出しを作ると、滞在時間の向上にもつながります。
関連する記事
競合との差をつける!高度な使い分けテクニック
キーワード活用をさらに一歩進めるには、「他の人はこちらも検索」とサジェストを状況によって使い分ける視点が重要です。ただ情報を並べるだけでなく、検索者の心理や行動の流れをとらえた分析思考が、競合と差をつける鍵になります。
検索フェーズ別に使い分ける分析思考
検索には「情報収集→比較検討→意思決定」といった段階があります。サジェストは主に検索前半の“興味・関心”を表し、一方で「他の人はこちらも検索」は、より深掘り段階の“比較・再検索”に現れやすいのが特徴です。
たとえば、「転職 方法」で出るサジェストは初期の悩み、「転職 年収 比較」で出るPASF(People Also Search For)は意思決定フェーズを示しています。こうした検索フェーズごとに出現傾向を読み解き、訴求ポイントを調整することが、精度の高いSEO戦略に直結します。
リライト時に注目すべきはどっち?使い方のポイント
既存記事をリライトする際には、検索ボリュームのあるサジェストを中心に見直し、タイトルや見出しを調整するのが基本です。一方、「他の人はこちらも検索」は、検索者が“どこで満足できなかったか”を読み解くヒントとして有効です。
たとえば、記事の直帰率が高い場合、「他の人はこちらも検索」に表示されたワードを新たに取り込むことで、ユーザーの期待値に近づけることができます。新規とリライトでは注目すべき視点が異なるため、目的に応じた使い分けが求められます。
まとめ|「他の人はこちらも検索」は検索意図の宝庫
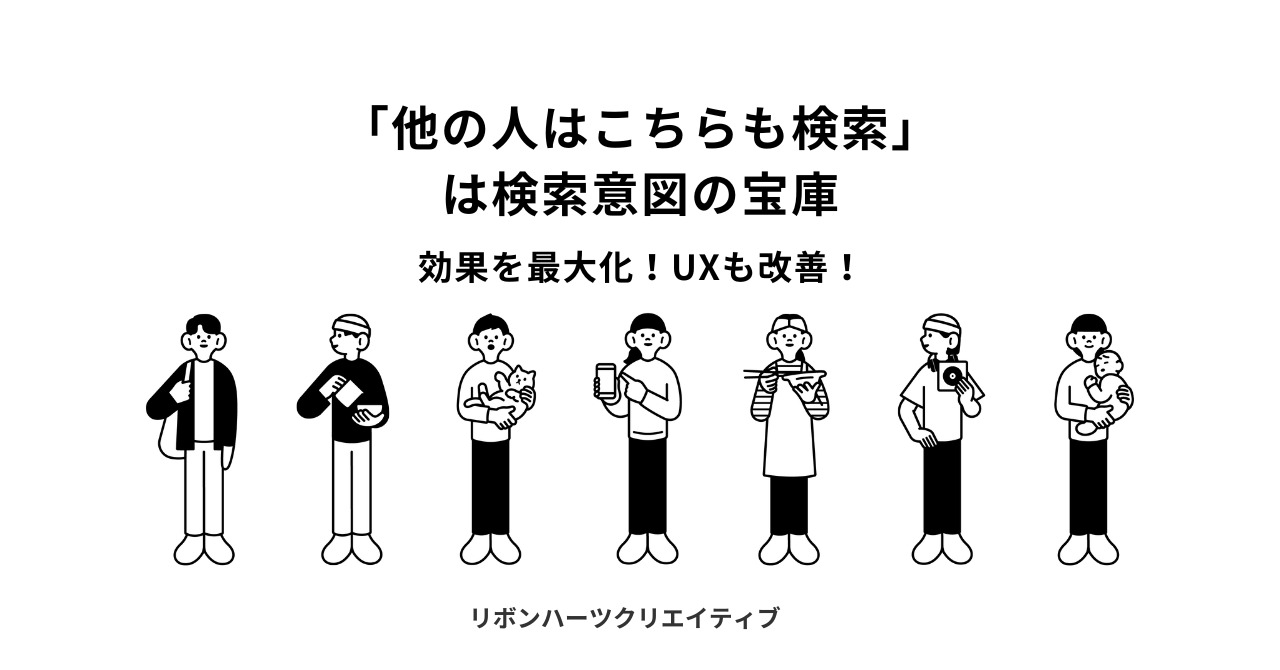
「他の人はこちらも検索」は、単なる関連キーワードではなく、ユーザーがどのように情報を探し、どこで迷っているのかを可視化できる貴重なヒントです。サジェストとは違う視点から検索体験を補完するこの機能は、コンテンツの質を高める材料として、SEOにもユーザー体験にも大きな効果を発揮します。
データ分析と組み合わせて成果を最大化
「他の人はこちらも検索」で表示されるワードは、実際の検索行動やクリック履歴に基づいており、ユーザーの“次の疑問”や“つまずきポイント”が見えてきます。これらをアクセス解析ツールやヒートマップと組み合わせて分析すれば、「どの情報が不足していたか」「どこで離脱が起きたか」といった具体的な改善点が明らかになります。
検索データとユーザー行動のクロス分析により、ただのリライトでは得られない深い改善が可能となります。
SEOだけでなくUXにもつながる使い方
この機能の活用は、検索順位を上げるだけではありません。ユーザーが本当に求めている情報を見極めて記事に反映することで、ページの**滞在時間や満足度(UX)**の向上にもつながります。たとえば、「次に知りたくなる情報」を事前に記事内に盛り込めば、ユーザーは再検索せずに済み、離脱を防ぐことができます。
つまり、「他の人はこちらも検索」は、SEOとUXを同時に改善できる“検索意図の羅針盤”といえるでしょう。
実践事例|顧客課題に寄り添う記事でSEOと成果を両立
リボンハーツクリエイティブでは、大建工業株式会社さまのWEBマガジン「ダイケンリフォームマガジン」を制作し、ユーザーの課題に寄り添う記事を通じて、SEOだけでなく実際の課題解決にもつながる成果を上げています
詳しい実績はこちら
ライタープロフィール

神澤 肇(カンザワ ハジメ)
リボンハーツクリエイティブ株式会社 代表取締役社長
創業40年以上の制作会社リボンハーツクリエイティブ(RHC)代表。
企業にコンテンツマーケティングを提供し始めて約15年。
数十社の大手企業オウンドメディアの企画・制作・運用を担当。
WEBを使用した企業ブランディングのプロフェッショナル。
映像業界出身で、WEB、紙媒体とクロスメディアでの施策を得意とする。
趣味はカメラとテニス、美術館巡り、JAZZ好き。